遺言には3種類ある
遺言の方式として、大きくは『普通遺言』と『特別遺言』の2つに分かれますが、特別遺言については特殊な環境下でのことなので、ここでは一般的な『普通遺言』について概略を説明します。
遺言を残す場合、『自筆証書遺言』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』のいずれかを選択することになりますが、具体的にこれらはどのように違うのでしょう?
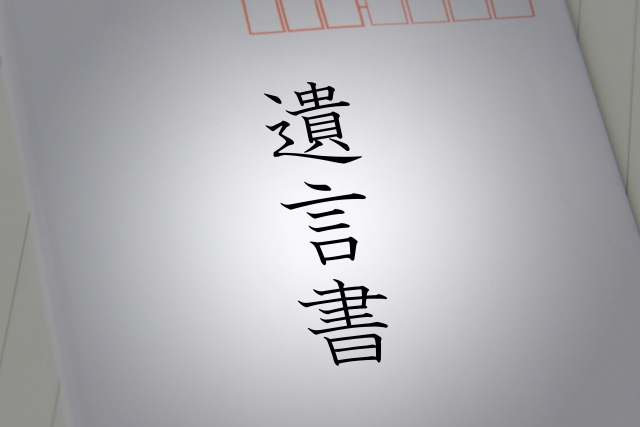
自筆証書遺言
自筆というくらいですから、自分で作成する遺言書になります。自分で書くだけですから特に誰かに相談する必要もなければ、費用が掛かることもありませんので、手軽に作成することが出来ます。
作成するには、基本的に全文、日付、氏名を自筆し押印します。
手軽に作成できる反面、保管方法によっては、紛失、偽造、変造、隠匿、破棄等のリスクがありますし、そもそも遺言書自体が発見されない、ということも考えられます。
また、正式な遺言書として各種手続きに使用するには、家庭裁判所による検認が必要になりますし、必要な要件を満たしていない場合には、遺言書自体が『無効』となってしまうリスクがあります。
※『自筆遺言書補完制度』を利用することでリスクを回避することも可能です。
公正証書遺言
公証人と証人2人以上の立会いのもと作成します。作成された遺言書は公証役場に保管されるので、自筆証書遺言のような、紛失や変造のリスクは回避することができます。また、家庭裁判所での検認を得ることなく有効な遺言書として扱われます。
実際に作成する(書く)のは公証人なので、遺言者が病気や障碍で筆記ができないという場合には、口述による対応ができます。
反面、公証役場まで出向く、証人を用意する、等の手間がかかりますし費用もかかります。
※遺言者が入院中など、公証人に来てもらって作成することも出来ますが、その分費用が嵩みます。
秘密証書遺言
封緘した自筆遺言書を公証役場へ持ち込み封印してもらうもので、公証役場には遺言書の存在が記録されます。
作成するのは自分なので、内容を自分以外の人に見られることがない点と、公証人が封紙に署名をすので、偽造、変造のリスクを避けることが出来るというメリットがあります。
また、遺言の内容を自筆でなくパソコンなどを使って作成することもできます。(署名は自筆が必要)
公証役場で公証人の下で手続きをするという点では『公正証書遺言』と同じですが、保管自体は自分で管理しなければならないので、紛失というリスクは残りますし、内容は自分だけしか知らないので、法的要件の不備で無効になる可能性もあり、裁判所での検認が必要である点も自筆証書遺言と同様です。
公正証書遺言よりは安価になりますが、費用がかかるという点は公正証書遺言と同様です。
一度書いた遺言を撤回したり変更したりできるの?
『遺書』というと、何やら人生の一大事のように捉え、一度書いたものは取り消せないと思われている方もおられるようですが、そんなことは全くなく、いつでも撤回(無かったこと)や、内容の変更(書き直し)も自由にできます。
基本的に遺言書が複数残された場合、作成日の新しいものが有効となります。なので、作成日のない遺言書は法的に無効となります。
また、公正証書遺言は新たな公正証書でないと撤回や変更ができないということもありません。ただし、公正証書遺言の後に自筆遺言を残した場合に自筆遺言に法的不備があって無効となった場合、前の公正証書遺言がそのまま有効となりますので、確実性を担保するには新たな公正証書遺言を残した方が安全といえます。
そもそも、遺言書というのは遺言者が亡くなって初めて効力が発生するものですから、たとえ遺言書に何を書いたからといって、生存中は遺言書の内容に縛られることはありません。
例えば、「所有しているA不動産をBさんへ贈与する」と遺言した後で、Cさんへ売ってしまうことも問題ありません。Cさんへ売った時点で「A不動産をBさんへ贈与する」という遺言は撤回されたことになります。
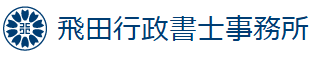
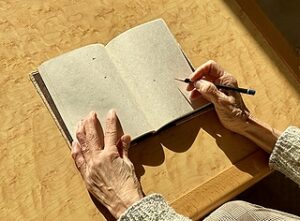

“遺言には3種類ある” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。