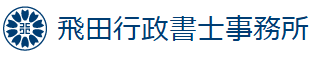遺留分請求には「時効」がある
「時効」ということば自体は、刑事ドラマなどでよく耳にするので、ご存知の方も多いと思います。罪を犯しても、一定期間経過すると起訴されなくなるという「公訴時効」ですね。(これは刑事訴訟法の話で、民事上の消滅時効とは全く異なる概念ですが、時効という言葉は馴染みがあると思います。)
ここでいう遺留分請求の時効とは、遺留分を請求することができる権利が消滅(なくなってしまう)ことをいいます。遺留分の請求というのは、「貸したお金を返して」というの違って、請求する相手に対して言い出しにくいという場面も多いかと思いますが、グズグズしている(一定期間経過する)と、時効によって請求することができなくなってしまいます。
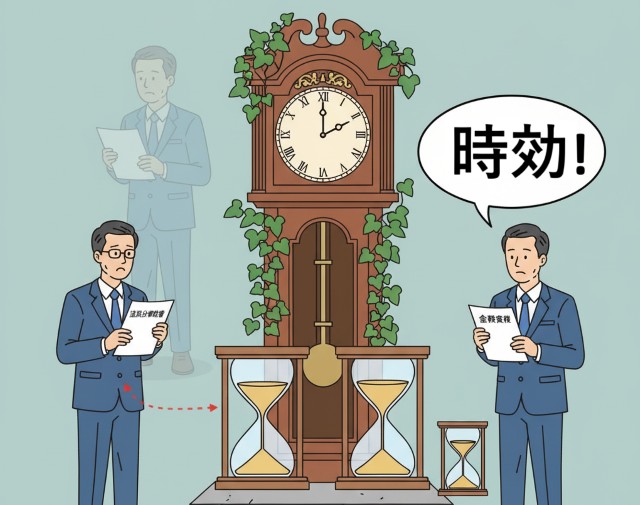
一定期間とはどれくらい?
法律で以下のように定められています。
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
民法第1048条 (遺留分侵害額請求権の期間の制限)
つまり、
①被相続人が亡くなった(相続の開始)
②自分に遺留分を請求する権利がある(贈与又は遺贈があった)
という2つの事実を知ったときから1年間グズグズしていると、請求の相手から時効を主張(援用)された場合、その後はもう請求できなくなります。
また、上記の2つを知らないとしても、被相続人が亡くなって(相続が開始されて)から10年が経つとやはり請求できなくなります。これは除斥期間といって相手方の主張(援用)がなくとも自動的かつ絶対的に権利が消滅します。
裁判所を通して請求しないといけないのか?
請求の意思表示をするだけでよく、裁判上での手続きを経て請求する必要はありません。極端な話、電話による口頭だけでも相手方にその意志が伝われば良いのですが、実務上は、後々言った言わないという争いを避けるとともに、時効との関係で、確定日付のある書面(内容証明郵便+配達証明)で通知するのが一般的です。
なお、この段階では具体的な金額を明示して行う必要もなく、「遺留分を請求します……」という意思を通知すれば足ります。
1年以内に請求しても5年経つと、やっぱり消滅?
遺留分侵害請求権を行使し、直ぐに遺留分を支払ってもらえればよいのですが、今度は相手方がグズグズしてなかなか支払ってもらえない場合、今度は金銭債権としての時効が問題になってくる場合もあります。
遺留分損害額請求により、受遺者または受贈者に対し金銭債権(お金を貰う権利)が発生することになりますが、この金銭債権にも消滅時効があり、権利を行使できることを知った時から原則5年経過すると消滅(なくなってしまう)ことになります。
「いつの話だよ、そんなのはもう時効だろう!」というセリフもよく聞くと思いますが、金銭債権にも消滅時効があります。
※金銭債権の時効に関しては、「債権回収」の話になってしまうので、ここでは詳細は省きますが、遺留分の請求に関する時効とは別に、金銭債権としての時効もあるという点は抑えておいた方が良いでしょう。