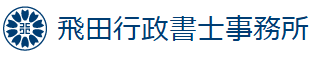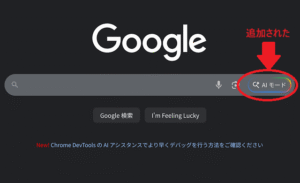遺留分の放棄について
今回は、遺留分侵害額請求権の放棄について書いてみます。
遺留分侵害額請求権とは、相続にあたり遺留分を侵害された相続人が金銭の支払いを請求する事ができる権利で、遺言書の作成に当たって特定の相続人に(遺留分を侵害するような)多くの財産を残そうと思っても、他の相続人から遺留分侵害額請求権を行使されれば遺言書の内容を実現することができないことになります。
このような事態を回避する方法はいくつかありますが、遺留分対策として最も確実な方法は「遺留分の放棄」をしてもらうことです。

相続発生前にも放棄できる
親の死により相続人となる子が「親が残した財産はいらないから……」と親の存命中に「相続の放棄」をすることはできませんが、「遺留分の放棄」は家庭裁判所の許可を得ることで可能です。
このため、遺留分を侵害するような内容の遺言書を確実に実現させたい場合などに、遺留分請求権利者となりうる相続人に対し、なんらかの代償を払い遺留分の放棄をしてもらうといったことも可能になります。
尚、民法に「撤回」に関する明文の規定はないものの、制度として「遺留分の放棄」は撤回ができますが、撤回するにも家庭裁判所の許可が必要であり、遺留分を放棄したことが客観的に見て不合理、不相当と認められるに至った等の事情がなければならず、放棄した相続人の気分次第で自由に撤回することが認められるものではありません。
裁判所への申立人は相続人
遺留分の放棄を家庭裁判所へ申し立てできるのは、遺留分を有する相続人であって、遺留分侵害額請求をしないようにしてもらいたい被相続人ではありません。「権利」を放棄するわけですから「権利を持っている人」しかできないのは当然ですね。
前述の遺言書作成のケースで言えば、申し立てできるのは他の相続人であって、遺言書作成者ではないということです。
尚、申し立人が未成年者の場合は、後見人が代理することになりますが、利益相反行為となるようなケースでは特別代理人の選任を請求する必要もあります。
許可されない場合もある
遺留分の放棄については、民法1049条に「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」とある通り、裁判所の「許可」が必要であり、これは形式要件を満たして通知すれば受理される「届出」と異なります。
裁判所が許可するかどうかの判断基準については、法律で明確にされているわけではありませんが過去の判例などにより、以下のようなものと考えられています。
1.遺留分の放棄が本人の自由意志に基づくものであること
2.遺留分放棄に合理的な理由と必要性があること
3.遺留分放棄を相当とするに足りる程度の合理的代償利益の存在が必要
ちょっと分かり難い部分もあるかと思いますが、ザックリいうと「申立人が①他の人間に強要されたわけでなく、自分の意思で、②何らかの理由があり、③既に遺留分に見合うだけの利益を得ている」から申し立てている。と裁判所に判断される必要があるということでしょう。
相続人であることに変わりはない
遺留分の放棄は、あくまで遺留分を請求する権利を放棄するに過ぎず、相続の放棄とは根本的に異なるので相続人としての地位に変わりはありません。
そのため、遺言書がなく遺産分割協議が必要な場合は当然に参加する必要がありますし、もし仮に被相続人に多額の負債(借金等)があった場合、相続放棄をしない限りその負債を相続してしまうことになります。
「遺留分は放棄する」との念書は意味がないか?
相続開始前(生前)の場合であっても、全く意味がないということはないでしょうが、意味を持つのはあくまで当事者同士で「このような念書があるのだから……」といった、話し合いの材料となる程度で、法的な「放棄」の効力は認められません。
相続開始後(死後)の場合であれば原則として有効で、家庭裁判所の許可は不要です。