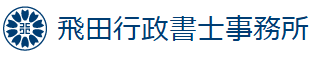祭祀承継って?
お盆休み真っただ中という方もいらっしゃると思いますが、お墓まいりには行かれたでしょうか?

ところで、エンディングノートや遺言書のひな型などを見ていると『祭祀承継の指定』といった項目が出てきたりすると思います。
「〇〇〇〇は祭祀承継者としてお墓を守ってください」 とか
「祭祀承継者として長男〇〇〇〇を指定する」 などといった例ですね。
そもそも、『祭祀』という言葉自体、普段の生活で使われることは少ないですし、いまひとつピンと来ていないという方もいらっしゃるようです。
『祭祀』という言葉を辞書で引いてみると
神や先祖を祭ること。まつり。祭典。
広辞苑 第四版
と説明されています。
国語的な言葉の意味はともかく、エンディングノートや遺言書で使われる『祭祀承継』は、「先祖を供養しお墓を守ることを、引き継ぐ」という理解で良いと思います。
祭祀という財産
民法では、相続人は、被相続人(亡くなった人)の財産全てを承継するのが原則(民法896条)だが、系譜、祭具、墳墓の所有権は『祭祀を主催すべき者』が承継する(民法967条)としています。
そして、この『祭祀を主催すべき者』というのは被相続人の指定する者で、指定のない場合には慣習により、慣習が明らかでないときは家庭裁判所が決める。としています。
さて、さて、ここでまた馴染みのない言葉が頻出してきました。
『系譜』『祭具』『墳墓』って何だ! って話です(^^;
私は学者ではないですし、葬儀関係の専門家でもないので詳しい説明はできませんが………
系譜…家系図のようなもの
祭具…位牌や仏壇といったもの
墳墓…お墓(注)
ということで。
よほどの由緒ある名家でもない限り、先祖代々の家系図があるという家庭も多くは無いと思うので、一般的に『祭祀財産=仏壇やお墓』のことという理解で良いと思います。
(注)墳墓=お墓としましたが、お墓といっても墓石や墓標だけのことなのか、それが置かれている墓地の所有権や使用権までいうのか?という点については、墳墓という言葉の意味としては墓石、墓標のことですが、墓地の所有権や使用権も祭祀財産に含まれるとの判例が出ています(広島高判平成12年8月25日)ので、ここでは墓石や墓標といった表現ではなく『お墓』としました。
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
民法 896条・897条
祭祀は負担?
家督制度も廃止され、そもそも『家』というものに対する観念が変化している現代では、旧来のお墓や仏壇といった「モノ」に縛られない形の提案も増えてきました。
更に、いわゆる「おひとりさま」といわれる、自分の死後にお墓の管理をしてくれる人がいない場合や、子供たちに負担を掛けないためにといった理由で、墓じまいを提案している書籍が書店の冠婚葬祭コーナーには数多く並んでいます。
大分昔の記憶で出典も明確ではないのですが、あるアンケートによると「自分の死後は先祖代々のお墓に入りたい」という回答が高齢者よりも20歳代の若年層の方が高かったという結果だったそうです。
遺言書の作成をきっかけに、「子供たちの負担を考えて墓じまいや永代供養も検討している」という方が時々おられますが、普段の何気ないやり取りの中で「俺は墓の管理なんてしたくねぇよ」といったセリフだけを真に受けたり、世の中の若者全てがお墓や仏壇に負担を感じているなどと考えるのはどうでしょう?
「自分もお墓の管理を負担に思い、このような負担は無くすべきだ」とお考えのうえで、次世代(子どもたち)にも自分の考えを伝えたいというのであれば良いのですが、ただ単に「負担に感じるだろうから…」というな思い込みだけで遺言書を作成するようなことは是非とも避けて頂きたいと思います。
お盆休みでお子様が帰省されているようであれば、お酒でも飲みながらちょっとだけ真剣にお墓の話をしてみるのも良いかもしれませんね。
ちなみに、祭祀の承継は前述したとおり民法に定められているれっきとした法律ですが、遺言において祭祀承継として指定された者がきちんとその役割を行わないことを理由に、負担付贈与の取り消しを求めた裁判において家裁での判例ですが『祭祀承継者は相続人の道徳的宗教的希望を託されてのみで祭祀を営むべき法律上の義務を負担するものではない』としています。