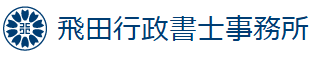来月から公正証書遺言書はオンライで手軽に作成「できるの?」
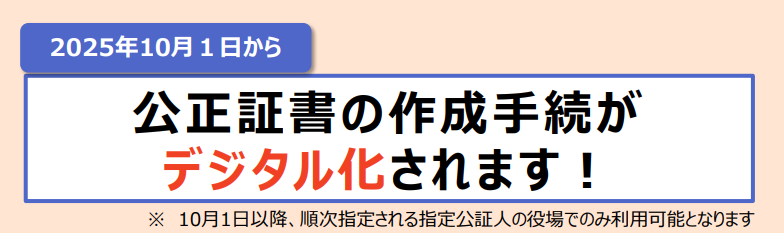
いよいよ来月から公正証書のデジタル化がはじまります。
公正証書のデジタル化は、令和5年6月6日に成立した改正公証人法(正式名称は「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」とひたすら長い(^^;)に基づくもので、現在紙媒体で作成されている公正証書について、電磁的記録で作成することについて困難な事情がある場合を除き、原則として電磁的記録をもって作成することとさ れました。( 改正公証人法36 条1 号)。
デジタル化といっても、オンライン(リモート)手続きが原則となるわけではない
「公正証書のデジタル化」という言葉と、SNS等ネット上で「困難な場合を除いて、原則、電磁的記録で作成」という改正法条文の一部抜き出しから、遺言書の作成においても直接公証役場へ行くことなくインターネットを利用したオンラインで作成ができると誤解されている方がいるようですが、ここでいう原則は記録と保存に関してで、これまでのように紙媒体ではなくデジタルデータ(PDF)として作成保存されるということで、原則として誰でも自由にオンラインによるリモートで公正証書が作成できるわけではありません。また、逆にインターネットによるオンラインでなければ作成できないというわけでもありません。
実際の手続きとしては、今まで通り作成者が直接公証役場へ行って手続きすることが原則で、「状況に応じてリモートでの手続きも可能になる」ということです。
近年、多くの行政機関による手続きがデジタル化されオンラインでの申請が可能となったこともあり、「デジタル化=オンライン申請」になるという誤解も無理のないことだと思いますが、公正証書遺言書の作成においては誰もが「オンラインで手軽に作成できる」といったことはないでしょう。
デジタル化で変わるのは公証役場、依頼者側はこれまで通り
デジタル化により、これまで紙媒体で作成保存していたものをデジタルデータ(PDF)として作成保存するようになったことで実務上変わるのは公証役場の問題であって、遺言書の作成をする依頼者側にとっては特に変わることはなく、押印が不要となる点と署名をPC(タブレット?)の画面にタッチペンで書くことになる程度ですから、「デジタル関係には疎いので敷居が高くなる」といった心配も必要ありません。
電磁的記録が困難場合とは
成年被後見人による公正証書遺言作成の際には、医師2人以上の立会いが必要で、立ち会った医師は「遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常態になかった旨を遺言書に付記して」これに署名、押印しなければならないとされていることから、法律上デジタルデータによる作成は困難と言えるでしょう。
また、保証意思宣明公正証書においても、民法上「署名し、印を押すこと」と明記されているため同様の理由で「困難な場合」に該当するといえます。
その他、一般的な判断根拠例として「スキャンが困難な規格外の大きな図面を引用して作成するよう場合」等が挙げられる思われます。
オンライン(リモート)による手続きができるケース
オンラインによるリモートでの手続きは、遺言者(依頼者)が一方的に行えるわけではなく、公証人が相当と認める場合に限られます。
公証人が相当と認めるにあたっての「相当」性の判断は「必要性」と「許容性」が考慮され、具体的には以下のようなケースが考えられますます。
【必要性】
- 遺言者が病気等で外出できない等の場合
- 公証役場が遠方であり過分の労力・費用がかかる場合、または参加者が多数でスケジュールの調整が困難な場合
- 離婚給付公正証書などの場合、DV 等により他方と直接対面しないことを希望する場合
- 感染症予防等により遺言者のいる施設や病院などへ外部者の立入りが許されない場合
【許容性】
- 本人確認、真意の確認、判断能力の確認等をオンライン上で行うことに疑義がある場合
- 高齢で認知症の傾向がみられる場合や、複数の推定相続人がいるのに合理的な理由なく一部の者に全ての財産を相続させる内容の場合など、事後的に紛争となる可能性が高いような場合
- これらのケースでは、リモートで行うことにつき慎重な判断がなされるでしょう。
- 最終的には依頼先の公証人の主観で判断されることになりますが、画面の外に影響を及ぼしそうな第三者が隠れていないことが確認できるかどうかいった点について、信頼できる立会証人が遺言者の自宅や病院等に赴いたうえで認める等といった判断をするケースも考えられます。
- いずれにしても、制度自体これからなので公証人も当初は慎重になるでしょうから依頼者の一方的な希望で安易にオンライン手続きができるとは考えないほうが良いでしょう。
今回の改正についての私見
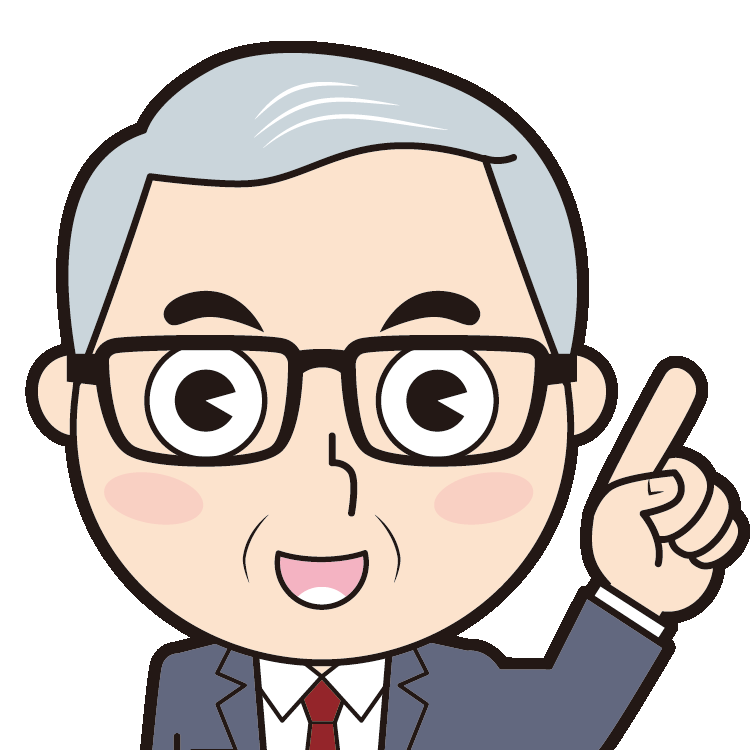
今回の記事は、「無料メール相談」への回答の補足という意味もあって作成したので、読み返してみると「依頼する側にとって大きく異なることはなくメリットもない」といった印象を与える内容になってしまいましたが、デジタル化の仕組みが整えば、より公正証書が活用しやすくなることは間違いないと思いますし、遺言書についても作成者だけでなく、実際に遺言書を活用する遺族にとってもメリットのあるものだと思っています。
半年ほど前にとある公証人の先生から聞いたお話ですと、神奈川県の公証人は総勢28人で、一人あたりの公正証書作成件数は東京よりも多く全国トップだそうで、欠員が出ても直ぐには補充されないということでした。
このため、遺言書の作成に当たって施設や病院への出張などもなかなか日程がとれないといったお話も伺いました。
オンラインによる公正証書の作成環境が軌道に乗れば、そうしたマンパワー不足の改善も期待できますが、そのためには利用者側においてもデジタル化に対応するための知識や環境の整備が必要になるでしょう。
弊所においてもそうした面でのフォローや的確なアドバイスができるよう、今後の動向を見守りたいと思います。
2025/10/22追記
リモート方式による電子公正証書の作成手順について、日本公証人連合会のYouTubeチャンネルにて説明動画が公開されました。
具体的な手順を動画で確認できるので、実際の手続きに関してイメージしやすいかと思います。
リモート方式を検討されている場合、視聴されてみると良いでしょう。