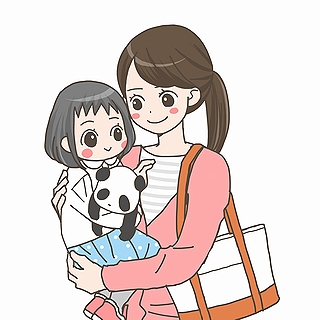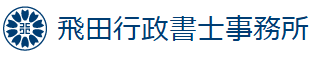未成年の子がいる現役世代こそ遺言書が必要
未成年の子どもがいるということは、おそらくまだ現役世代ということでしょう。この年代ですと、自分に万一のことがあっても遺された子どもが困らないよう、生命保険に入っている人は多いと思いますが、遺言書を書いたという人はほとんどいないように思われます。
相続が発生したとしても、子どもがいる場合の相続人は配偶者とその子どもたちで、親や兄弟姉妹は関係ないから遺言書がなくても問題ないと思いがちですが、遺言書がないといろいろと面倒なことになってしまいます。

遺された配偶者がすべて相続するわけじゃない
未成年の子と配偶者を残して亡くなった場合、遺された方の親が子どもを育てていくことになるので、相続もその親が受けるのが道理のように思われますが、「法定相続分」という決まりがあるので、そう簡単には行きません。
法定相続分とは、民法で定められている相続人の相続割合で、遺言による指定がない場合の基準となり、配偶者と子どもが相続人となる場合ですと、配偶者と子どもが各々2分の1ずつで分け合うこととされています。
これは子どもが自分でお金を使うことができないような幼児であってもかわりません。
特別代理人を選定することになる
遺言書がなく配偶者と子どもが相続にとなった場合、配偶者と子供で遺産分割協議を行う必要がありますが、未成年である子どもは単独で法律行為はできませんので代理人が必要となります。
子どもの代理人は通常であれば親権者である親になるので、遺された方の配偶者が代理人として手続きを進められるかというと、法律には「利益相反」という考えがあり、利害関係のある配偶者が代理人となることはできず、「特別代理人」を専任しなければなりません。
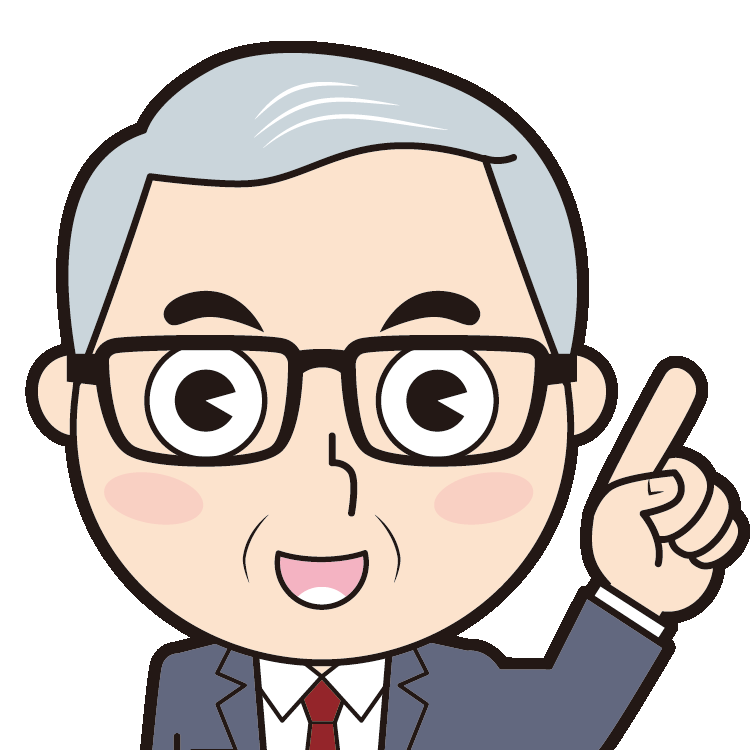
利益相反とは
ある行為によって一方の立場では利益になるものの、他の立場では不利益になることを指します。
今回の場合、配偶者の利益を多くすると、子どもの利益は少なくなるという関係になるので、配偶者と子どもは利益相反の関係となってしまいます。
特別代理人は家庭裁判所へ特別代理人候補者を決めたうえで「特別代理人選任の申立」を行い、裁判所の決定を待たなければなりません。
遺された配偶者の負担
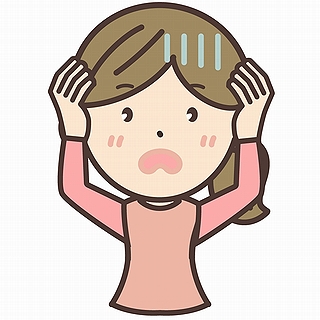
特別代理人となってくれる人を決めて、裁判所へ申立を行うという行為自体も、遺された配偶者にとっては労力、精神面でかなりの負担になります。また、特別代理人候補者を決めるといっても、親族など無償で頼める適当な人がみつからない場合、代理人への報酬という形で実質的な費用負担も発生することになります。
この場合、子どもが一人であれば代理人も一人で済みますが、子どもが複数いる場合、一人の代理人が複数の子供全員の代理人となることはできないので、子どもの数だけ代理人を専任しなければならず、その分費用負担も増加してしまいます。
更に、専任された代理人と「遺産分割協議」を行い書面として残す必要があるので、専任された代理人次第では、配偶者にとって負担に感じるケースも少なくありません。
遺言書があれば
遺言書さえあれば、特別代理人の選任も遺産分割協議書の作成も必要なく、すべての手続を配偶者だけで行うことができます。
「まだまだ現役時代で遺言書なんて頭の片隅にもない」かもしれませんが…万一の際に遺された配偶者のことを想うのであれば、ぜひ今のうちに遺言書を書いておくことをおすすめします。
あれこれ考えすぎて複雑な遺言書にする必要はありません。「すべての財産を配偶者へ相続させ、遺言執行者として配偶者を指定する」という一文でいいのです。
まだまだ、この先何があるかわからない世代ですから、書き直しや破棄するケースも想定し、費用をかけて公正証書遺言書にしておく必要もありません。
夫婦でお互いを相続人にした遺言書を作成し自宅で保管しておくだけでも良いでしょうが、実際に相続が発生した際の裁判所の検認手続や遺言書の紛失などといったリスクを考えると、法務局による「自筆証書遺言書保管制度」を利用しておけば完璧でしょう。