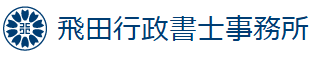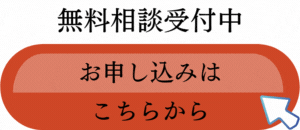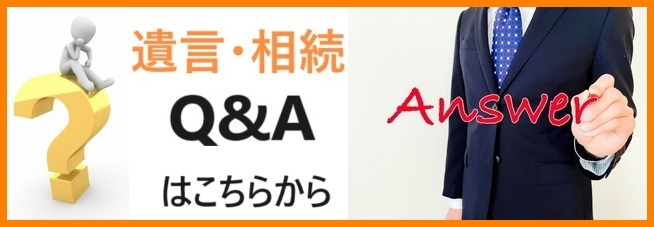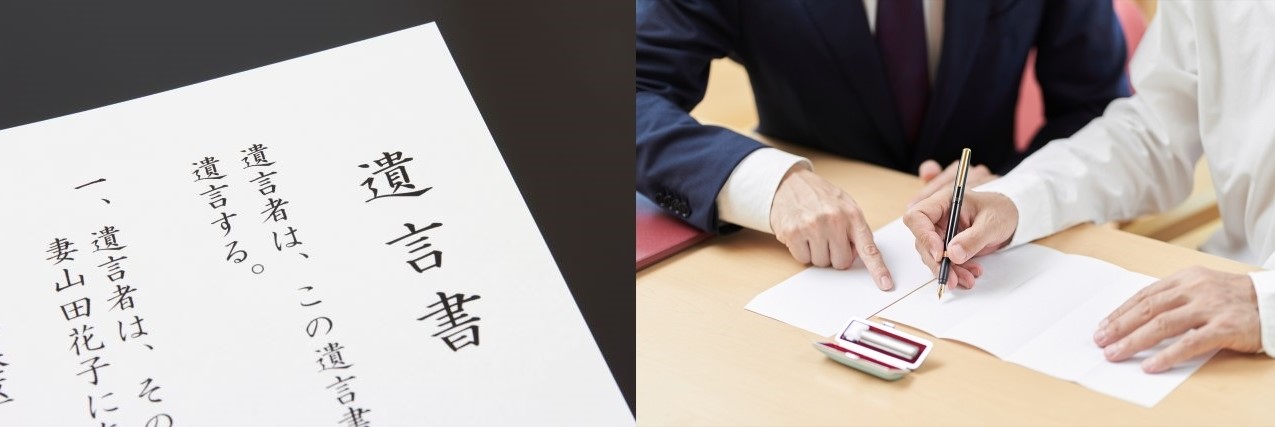
相談密度の濃い『遺言書作成サポート』横浜
公正証書遺言書・自筆証書遺言書
想いを伝え実現する遺言書を作成します
遺言書を作成するのにサポートを受ける必要はあるのか?
「遺言書の書き方」を謳った情報は書店やネットに溢れています。実際、遺言書の文面はある程度定型化されていますので、これらの情報を基にとりあえず遺言書を作成することは難しい事ではありません。
多くの書籍やネット上の記事で指摘されている自筆証書遺言書作成時の形式や要件についても、複雑な内容でなければ法的に無効になってしまうということもそれほど多くないと思います。(裁判所も出来る限り遺言書は有効なものとして扱おうという方向です)

それでは、お金を払って専門家のサポートを受ける意味はどこにあるのか?
それはズバリ…
お客様自身が、遺言書をを作成する目的(希望)を実現するために最良の判断を下すため!
です!
そのために、知識と経験を持った専門家のアドバイスを受け、参考にしながら遺言書の内容を熟慮することができる点に対価を支払う意味があります。
戸籍類の収集や公証人とのやり取りなど、面倒なことを全て任せたいといったこともあると思いますが、そうした手続きだけであれば極端な話し一定のスキルと資格があれば誰でも良いので、単純にコスト重視で判断すればよいでしょう。また、そうした手間暇も惜しまないということであれば公正証書にしても自筆遺言書保管制度を利用するにしても、全てをご自身で行うことも可能ではあります。
遺言書の作成を専門家に依頼するということは、安心、安全に、対価を払いたいと思う付加価値を望むかどうかということになると思います。
弊所の遺言書作成サポートは
「お客様に寄り添うサポート」をポリシーに、お客様の想いを伝え実現させるため、私自身のこれまでの人生経験と専門家としての知識により誠心誠意ご相談にのらせていただきます。
弊所の『遺言書作成サポート』を利用するメリット

相談密度の濃さ
問合せや相談の際に一方的な考えを押し付けたり、法律の規定のみに縛られたアドバイスしかできないようではいけないと考えています。
弊所の『遺言書作成サポート』を利用する最大のメリットは、お客様一人ひとりの状況に応じた相談密度の濃さにあります。遺言書の作成を検討されているからには、お客様個々の理由・想いがあるはずです。
そうしたお客様個々の気持ちに寄り添うことなく、単に法律的な側面での定型的なアドバイスだけでは報酬を支払ってまで相談する意味がありません。時には人生経験を基にした泥臭いアドバイスも必要ですし、弊所ではフィナンシャルプラニング技能士としての見地からのアドバイス(保険商品等の営業、販売は行っていません)も併せてご相談にのらせていただきます。
遺言書原案についてのご相談は、何度でも追加料金は一切いただいておりません。ご相談者様が「これで安心だ、ホッとした」と心から思っていただける遺言書の内容になるまでトコトンお付き合いさせていただきます。

遺言書見直し永久サポート
遺言書は作成したら終わりとは考えておりません。定期的に見直しのご案内をさせていただくことで永続的な安心をお届けしています。
遺言書は、いつでも変更または撤回ができます。
人生は常に変化しています。財産状況や相続人に変化があるかもしれませんし、ご自身の気持ちに変化があるかもしれません。
定期的に見直し現状を再確認することでスムーズな相続が行え、残された遺族の負担を軽減することになります。
また、たとえ何の変化もなく見直す必要が無いと思える場合でも、少なくとも年に1度は見直して、何事もなく無事に1年過ごしてきたことを喜び、遺言書へ記した相続人、遺贈者への気持ちを新たにすることも無駄ではないと考えております。
弊所が存続する限り年1回の遺言内容見直しのサポートを無料で実施しています。

寄り添うサポート
法務局や公証役場への訪問に不安を感じる場合や、ご高齢のおひとりさまで外出に不安を感じる場合にもしっかりサポート致します。
いずれも手続き自体はお客様ご自身になりますが、ご希望があれば法務局や公証役場へ同行させていただきますのでご安心ください。
市町村役場とは違って、法務局や公証役場というのは一般的にはあまりなじみのない場所のため「何となく訪問に不安を感じる」という方もいらっしゃるかと思います。また、ご高齢でおひとりの外出が不安な方や車いすをご利用の方でも、私自身両親の介護で車いす介助は経験済ですので安心してお任せください。
遺言書の悩みを無料で相談
- 遺言書を作成しておくべきか悩んでいる
- 遺言書について色々調べてみたが専門用語の意味が良くわからない
- 弊所のサポート内容についてもっと詳しく説明してほしい
といったお客様のために、初回無料相談を行っております。
ご希望の日時にご自宅まで伺いご相談させていただきますので、わざわざ来所いただく手間もかかりませんし、実際にご依頼いただくまで費用は一切かかりません。
サポート内容と料金
自筆証書遺言書作成サポート
自筆証書遺言書作成サポートでは、『自筆証書遺言書保管制度』の利用を前提とし、3つの”安”をお届けいたします。
| 安心 | 遺言書の内容について、法務・実務の両面からアドバイス 相続開始時に指定人へ遺言書保管を通知 裁判所による検認手続きが不要 |
| 安全 | 作成した遺言書は国(法務局)が保管 |
| 安価 | 公正証書作成費用・証人への謝礼が不要 |
お客様に代わって戸籍類を取得し、相続関係説明図、財産目録を作成のうえ、遺留分を考慮しつつ遺言書の内容についてご相談に乗らせていただき原案を作成いたします。
ご納得いただける遺言書完成後、法務局への自筆証書遺言書保管申請手続きのご案内をいたします。
具体的なサポート内容
▶遺言内容についてのご相談・アドバイス
▶住民票・戸籍類の取得代行
▶推定相続人の確定、相続関係説明図の作成
▶財産目録の作成
▶遺言書原案の作成
▶原案についてのご相談・調整
▶自書された遺言書の最終チェック
▶法務局への遺言書保管手続きのご案内
▶法務局への同行
▶遺言書見直し永久サポート
※推定相続人確定までに3通を超える戸籍が必要な場合、4通目より1通につき2,000円の追加報酬となります。
※各証明書の交付にかかる手数料、郵送代等の実費は別途ご請求となります。
※法務局同行(任意)時の交通費実費は別途ご請求となります。
※法務局による自筆証書遺言書保管制度の利用手数料3,900円が別途必要となります。
報酬額(税・実費別) 73,000円
公正証書遺言書作成サポート
想像以上に手間のかかる戸籍類の収集から公証役場との調整まで経験豊富な行政書士が責任をもってお手伝いさせていただきます。公証役場へも同行し追加料金なしで証人もお引き受けいたします。
具体的なサポート内容
▶遺言内容についてのご相談・アドバイス
▶住民票・戸籍類の取得代行
▶推定相続人の確定、相続関係説明図の作成
▶財産目録の作成
▶遺言書原案の作成
▶原案についてのご相談・調整
▶公証人との内容調整
▶公証役場への同行
▶遺言書見直し永久サポート
報酬額(税・実費別) 88,000円
※推定相続人確定までに3通を超える戸籍類が必要な場合、4通目より1通につき2,000円の追加報酬となります。
※各証明書の交付にかかる手数料、郵送代等の実費は別途ご請求となります。
※公証役場同行(任意)時の交通費実費は別途ご請求となります。
※公証役場への支払いが別途必要となります。
※証人を依頼する場合は別途費用が発生します。(1名分)
自筆証書遺言書保管手続きとは
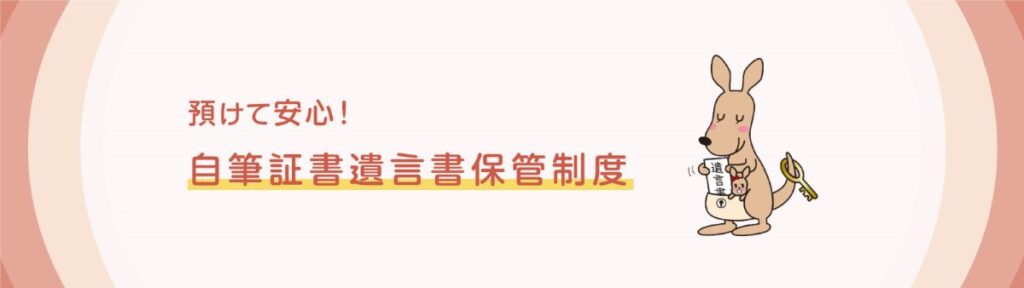
画像引用元:法務省ホームページ
『自筆証書遺言書保管制度』とは、これまで自筆証書遺言書の欠点とされていた問題を解消するため2020(令和2)年7月から開始された国の制度です。
この制度を利用することで、遺言書の紛失・亡失、相続人等の利害関係者による破棄、隠匿、改ざん等の危険を防ぐと共に、裁判所による検認が不要となります。
また、作成した遺言書を自分の死後、相続人が読んでくれるか?という根本的な問題についても、『死亡時通知』という制度により、希望すれば、戸籍担当部局と連携して遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合に、あらかじめ遺言者が指定した方に対して、遺言書が保管されている旨を知らせてくれます。これは、公正証書遺言書にないメリットといえるでしょう。
『自筆証書遺言書保管制度』を利用する場合、遺言者ご本人が直接法務局へ出向く必要がありますが、公正証書を作成するにしても原則ご本人が公証役場へ出向く必要があります。
弊所の「自筆証書遺言書作成サポート」では、法務局への予約方法、申請書記入時の注意点、申請窓口での対応等、詳細にご説明させていただきますのでご安心ください。また、ご希望があれば申請法務局までの同行を承っています。
※保管制度については、以下のブログ記事もご参照ください
➡『自筆証書遺言書保管制度』とは?
➡遺言書保管してもらいたいけど、法務局ってどんなとこ…
公正証書作成にかかる費用

手数料
公正証書遺言書を作成するには、公証人へ支払う手数料が必要になります。手数料は遺産総額(遺言書に記載する)により以下の通りとなります。
| 遺産総額 | 手数料 |
|---|---|
| ① 100万円以下 | 5,000円 |
| ② 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
| ③ 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
| ④ 500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
| ⑤ 1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |
| ⑥ 3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |
| ⑦ 5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
上記の手数料に加え、遺産総額が1億円以下の場合「遺言加算」といって11,000円が加算され、用紙代として数千円程加算される場合があります。
手数料の計算で注意が必要な点として、遺産を受け取る「人ごと」に計算して「合計」されますので、遺産総額を単純に上記に当てはめて計算するわけではないということです。
例として、3,000万円の遺産を配偶者に1,500万、子供2人にそれぞれ750万づつ相続させる場合ですと、遺産総額が3,000万円だから手数料は上記表⑤の23,000円というのではなく、以下の計算式になります。
手数料=配偶者⑤<23,000円>+子供④<17,000円>+子供④<17,000円>=合計57,000円
上記手数料<57,000円>+遺言加算<11,000円>+用紙代<仮に2,000円>=70,000円が手数料合計ということになります。
因みに、公証役場の費用は原則全国一律で、お住まいの市区町村に限らずどこの公証役場でも手続きは可能です。(公証役場によっては、予約が取れず数か月待ちということになる場合もあります)
※公証役場の所在地については、こちらのブログ記事をご参照ください➡神奈川県内の公証役場所在地
証人費用
また、公正証書遺言書を作成する場合には証人2名の立会いが必要となり、その費用も公証役場への費用とは別にかかることになります。費用に決まった額はありませんが、相場として一人当たり1,0000円~15,000円程度と考えておく必要があると思われます。
ご自身で費用のかからない人に頼むことも可能ですが、未成年者や推定相続人・受贈者とこれらの配偶者・直系血族は証人にはなれませんので、近しい親戚にはほとんど頼めないということになります。(証人には遺言内容を知られるという問題もあります)
※弊所『公正証書遺言書作成サポート』の場合、ご希望により無償で証人をお引き受けいたしますので、証人を頼める当てが無いといった場合でも、実際にかかる費用は一人分で済みます。
自筆証書と公正証書どちらを選ぶべきか
遺言書の作成をお考えの場合、お客様個々の『理由・想い』があるはずで、それによってどちらを選択すことが最も良いのか?ということになります。
『理由・想い』はお客様お一人おひとりによって異なるため、一般論としてそれぞれのメリット、デメリットを挙げてもあまり意味のあることではありません。
書籍や専門家のサイトでは、多くの場合「公正証書遺言書」をすすめていますが、その理由として挙げているものの大部分は「自筆証書遺言書保管制度」により解消されることとなりました。
このような事情から現在弊所の基本的な考えとしては、コストパフォーマンスの点で先ずは法務局による自筆遺言書保管制度の利用を前提とした『自筆証書遺言書』を検討していただき、以下のような理由がある場合に『公正証書遺言書』を検討していただいております。
- ご自身で筆記が出来ない
- 傷病等で外出が出来ない
- 認知能力に疑義があり、後々遺言能力の有無で争いが生じる可能性がある
- 法定相続人の中に相続発生の事実を知らせたくない人がいる
ただし、稀に「公正証書が正式な遺言書であって、それ以外の遺言書は公式な書類ではない」といった誤った考えを持たれている方もいますので、そうした場合に公正証書であればすんなり受け入れられたものが自筆証書であったために無用なトラブルになってしまうという可能性があるかもしれません。
※こちらのブログ記事もご参照ください➡自筆と公正証書、どちらが正式な遺言書?
いずれにしても、冒頭にも書いた通りお客様個々の『理由・想い』『立場や状況』によって、どちらを選択するか判断が分かれることになります。
尚、お客様の状況によっては必ずしも費用をかけて遺言書を作成するまでもなく、いわゆるエンディングノートでご希望を果たせる可能性もあります。あくまでお客様のご希望次第ですが、弊所ではそのようなケースでは初回ご相談時にその旨ご提案しています。
遺言書作成Q&A
【遺言・相続】に関するブログ記事
- 新年を迎えるにあたり、自分と向き合い心を整理する
- 遺留分請求には「時効」がある
- 遺留分の放棄について
- 来月から公正証書遺言書はオンライで手軽に作成「できるの?」
- 未成年の子がいる現役世代こそ遺言書が必要
- 「夫婦二人きりなので相続で揉めることはない」は危険!
- 異母兄弟が相続人となる場合
- 配偶者の連れ子と養子縁組した後、その配偶者と離婚した場合
- 婿養子が亡くなった場合の相続
- 1月5日は遺言の日
- 遺言書作成「まだ早いは禁物」大切なのは健康寿命
- お墓の相続について
- 投資信託を相続させる遺言書
- 行方不明の相続人がいる <失踪宣告>
- 「相続放棄」と「相続分の放棄」
- 遺産分割協議前に預貯金の払戻を受けるには
- 年末年始は遺言書に向き合う絶好のタイミング
- 相続した預金口座はいつ凍結される?
- 自筆証書遺言書における財産目録作成時の注意点
- 遺産分割前に貸金庫にある現金の一部を持ち出すことはできるのか?
- 遺言書があれば内縁の妻も預貯金を払い戻せるのか?
- 自分でつくる遺言書 〜失敗しないための考え方・書き方〜
- 全く交流のない異母兄弟のいる遺産分割協議
- 仲の良かったきょうだいがなぜ相続で揉めるのか
- 祭祀承継って?
- タイタニックの乗客が遺言するには
- パスワードのわからない故人のパソコンをなんとかしたい
- 遺産分割の際の不動産価格は「相続税評価額」?
- 【番外編】相続の基本をAIに説明させてみた
- 相続税を申告し納税する